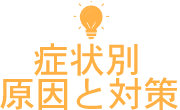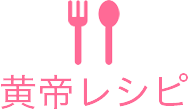暮れなずむ街を、可南は急ぎ足で歩いている。待ち合わせの時間が近づいているのもあるが、少しでも早く細見に会いたい、彼の顔が見たいという気持ちに、身体が操られているような感覚だった。
あの日からもう五日が経ったのだ。細見にやさしく抱き寄せられた感覚は、まるで一秒前のことのように生々しく身体に残っている一方で、会えない間が途轍もなく長く感じられ、可南は自分の時間感覚の狂いを、愛しさを込めて自嘲した。
「ここか」
お互いのスケジュールを突き合わせると、次に会えるのは金曜日の夜だけだったから、とりあえず日時だけは決めていたのだが、昨夜、細見から「明日はここに来てください。店のことは調べないで」というメッセージとともに、住所だけが送られてきたのだった。
「焼き鳥屋さん、なのね」
そう独り言を言いながら縄のれんをくぐり、ガラガラと大袈裟に音を立てる引き戸を開ける。その瞬間、中から肉の焼かれるいい匂いがうわっと可南を包む。少し煙たくて目を瞬いていると、奥の方から「こっち、こっち」と言う細見のよく通る声が聞こえた。
狭いテーブルの間を何度も「すみません」と言いながら体を横にして通り、ようやく細見の前に座る。
「可南さんはこんな店、来ないでしょ」
「そうね、とくに最近はなかなか。学生の時も、私、東京だったから……」
「そんな可南さんに、今日は博多の焼き鳥を味わってもらおうと思いまして。それになんというか、ちょっとしたタイムスリップを楽しもうという趣向です」
「タイムスリップ……」
言われてみれば、店全体が昭和の趣である。あえてレトロな演出を施しているのではない。きっと、創業から変わっていないのだ。小さな木のテーブル、ちょっと不安定な丸椅子、たっぷりと脂を吸い込んだ壁を裸電球が照らしていて、それを隠すように貼られたビール会社のポスターも、しかし今や年季ものだ。
「今日は生ビールから始めたいんですが」
「おまかせします」
うなずいた細見はせわしなく動いている店員をタイミングよくつかまえて、「とりあえず生二つと、皮十本」と伝えた。
「皮だけを? 十本も?」
可南は思わず目を見開いた。
「あれ? あ、そうか。可南さんは非常識なんですね」
細見はいたずらっ子のように笑う。
「こういう店だとね、とり皮は十本単位で注文するのが今やコモンセンスなんです。二人だから二十本と言いたいところを、自分に抑制をかけて十本にしたくらいですから」
得意げに話す細見の笑顔を、可南は失礼だとは思いながら「かわいい」と感じた。
「もちろん、博多の焼き鳥文化の筆頭が『豚バラ』なのは周知の事実です。それこそ昭和の頃は、豚バラを十本単位で注文する人は珍しくなかった。無料の酢キャベツと一緒にそれをバクバクやるのも確かに博多の焼き鳥の醍醐味です」
テーブルに届いた生ビールのジョッキを、ガチンと少し派手に合わせて乾杯すると、細見は一気に3分の1を喉に流し込んだ。
「それで言うと、とり皮のグルグル巻きは、比較的新しい文化と言えますよね。発祥の店では昭和四十年台の始め頃から出していたそうですが、このスタイルを取り入れる店が増えてきたのが二十年くらい前ですかね。今や博多の焼き鳥の一つの代名詞と言っても過言ではない……」
「ねえ、ご高説の腰を折るようで悪いけど」
可南はすでにこれくらいの軽口が言えるようには細見に打ち解けている。
「私、その『グルグル』は初めてだから、先にどんなふうに調理するか教えてもらえません?」
「ああ、さすが、料理研究家。やっぱりそこが気になりますか。まずはとりの首の皮を串にグルグルと巻きながら刺していきます。それをね、六日間かけて、素焼き、タレ焼き、寝かせを繰り返すんだそうです」
「六日も掛けるの? なんというか、執念を感じるわね」
「それが一本百円もしないんですよ。博多は焼き鳥天国です」
細見の講釈が終わるのに合わせたように、皿に整然と並べられた「とり皮」が運ばれてきた。細見に目で促されて、可南が先に串を取り、茶色に輝くとり皮を歯で引き抜くようにして口に入れる。
「わ、なにこれ。カリカリでサクサク!」
後に続いた細見がうなずく。
「あ、でも、中は意外とジューシーなのね。ただ、脂はいやらしく感じない。そうか、何回も下焼きを繰り返すことで、余分な脂が落ちているからね。ああ、だめ。ビールが進んじゃう。そして何本でも食べられそう」
先ほどまであんなにも雄弁だった細見は、うれしそうな微笑を浮かべて、驚く可南を見ている。その後二人はさらに十本を追加したとり皮をビールとともにあっさりと平らげた。
「よし、可南さん、じゃあ次の店に行きましょう」
「えっ、もう出るの? だって、ここに来て、まだ1時間も……」
「いいから立って」
細見はさっと伝票を取ると、可南の手を握って少し強引に席から立たせ、「今日はぼくの言う通りにしてください」と耳元でささやいた。可南は耳にかかった息で、ぞくぞくした自分を少し恥ずかしく思いながら、手を引く細見に自分を預けて店を出た。