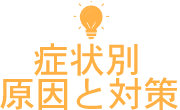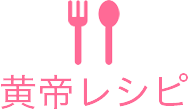「そんなに遠くないから、このまま歩いて行くよ」
可南は細見に手を引かれ、彼のペースに合わせるようにして歩いている。それは初めて見る男らしい一面で頼もしく、敬語を使わずに話してくれたこともうれしかった。可南は細見の横顔に「うん」とだけ答える。
「はい、到着。二軒目はここ」
細見は福岡の街の中心部に並ぶ屋台の一軒を指差し、にっこり笑ってのれんをくぐる。
「お、細見さん、毎度。お二人さんね。そっちの角に座ってくれる」
店主は五十代の半ばといったところか、料理人というよりも学者のような知性を漂わせている。夫婦二人の経営なのだろう。妻のほうは「世話好き」の性格が笑顔からにじみ出ている。
「可南さん、屋台なんて来ることないでしょ」
「そうね、何年ぶりかしら。いや、何十年ぶり?」
「地元の人は屋台をよく利用するって思われてるだろうけど、実際は『あんまり行かない』という人が大半だよね」
「私が若い頃は違ったけど、今は観光客のためのもの、という感じがする」
そう言った後、可南は細見に耳打ちする。
「それに、ほら、意外とお安くないし……」
細見は笑顔でうなずく。
「そんな可南さんを、今日は驚かせてみせるからね。ご主人、風が涼しくなると、あれを食べたくなるんだよね。入ってます?」
「銀杏? あるよ」
「おお、ラッキー。可南さん、ここの銀杏は藤九郎ぎんなんと言って」
「ああ、岐阜の!」
「さすが。それが仕事だとはいえ、よく知ってるね。ぼくはこの銀杏が日本一だと思ってるんだ。しかも味付けが……」
細見の説明を遮るように可南の前に皿が置かれる。大粒の銀杏はすでに殻が剥いてあり、煎ってあるというより、油で焼かれた感じだ。一粒、口に含む。
「バター? わあ、これは思いつかなかったけど、銀杏の苦味とバターの甘味が調和して、ああ、はあ……幸せ」
「美味しいものを食べるときの、可南さんは本当にきれいだ」
可南は「ちょっと」と言いながら、細見の袖を引っ張って、「周りに聞こえます」と続けた。
「別にいいじゃない。ぼくの本心だから。誰に聞かれたって恥ずかしくない」
細見はそう言ってから、松茸のホイル焼を注文した。走りの、しかも外国産の松茸だが、しっかりととった和出汁と多めの三つ葉で香りを加えているあたり、店主は料理のことを深く学んだ人に違いないと、可南は確信した。
「それで、これは裏メニューだからこっそり注文しなきゃなんだけど……」
細見はいたずらをたくらむ少年のような顔で店主に目配せをして、まだ汁の残ったホイルを渡した。無言でうなずいた店主は、その五分後、可南の目の前に、見たことのない鉄板料理を置いた。
「なに?」
「特製、松茸の焼きラーメン。すごいでしょ」
なるほど、立ちのぼる湯気が松茸の香りを可南の鼻腔に運んでくる。
「すごいけど、だめ、私、おなかいっぱいで……」
「いや、絶対にいけるから。一口でいいから食べてみて」
今夜の細見はいささか強引だが、可南はそれを楽しんでいる。実際に麺をすすると、上品な豚骨スープの味の向こうから、複層的な香りがやってきて、それが後を引く。チャーシューにキクラゲ、ネギといった豚骨ラーメンの定番の具材がこんなにマッチするのも驚きだった。
「これ、最高……」
「ほら、言った通りだ。可南さんはね、自分にブレーキをかけすぎなんだよ」
「ブレーキ? そう?」
「そうだよ。可南さんは、自分で思っているよりもずっと若い。店のはしごだってできるし、締めのラーメンも食べられる。ぼくは時折、可南さんの、その成熟した女性の魅力の奥に、少女を感じる。可憐な少女をね」
「なんだか、恥ずかしい」
「だからさ……」
饒舌だった細見が急に口ごもる。
「どうしたの?」
「だから、昔のことは忘れられないかもしれないけど、時を戻してもっと若い頃に出会うこともできないけど、ぼくたちは今からでも始められると思うんだ。若い頃のような経験がしたいと思ったら、今日みたいにできる。もちろん、大人の時間も過ごせる」
「屋台でプロポーズ?」
可南はちゃかしたが、細見の表情はゆるまない。テーブルの下の可南の手に、細見の手が重なる。
「ぼくじゃ、不足?」
「そんなことない。私のほうこそ。だって、私……」
「何度も言うけど、歳なんて関係ない。それに可南さんは若い。きっと、永遠に」
細見の手に力がこもる。
「なにが障害なんだろう。ご主人のこと?」
「それは……」
違うと断言できない自分に、可南は戸惑っていた。細見は重ねていた手を離して、「よし、じゃあ、女将さん、お勘定」と明るい声で言った。
「今日はこれで帰りましょう。次は可南さんから連絡してください」
うなずくしかない可南に背を向けて、細見は雑踏の中に消えていった。