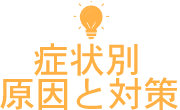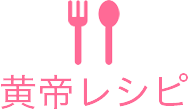「私、亡くなった夫の声が聞こえるの」
可南の声はふるえながらも、その奥には凛とした響きがあった。細見は一瞬、目を見開いたが、すぐに表情を戻して口角を上げ、告白の続きを促した。
「もう少し正確に言うならば会話なんです。彼の声が聞こえて、私がそれに答えたら、また彼が返してくるみたいな。電話に似てるけど、頭の中だけでやりとりしている感じ……」
細見は柔和な表情で、じっと聞いている。
「夫が亡くなってからすぐのことでした。私、自分がおかしくなったと思って。だって、変ですよね、死んだ人の声が聞こえるだなんて」
「確かに変ですね。うん、すごく変だ!」
細見はそう言って、明るく笑った。可南もつられて微笑む。
「でも、ぼくは信じます。ぼくには霊感みたいなものはないけど、でも魂の存在は信じています。音楽に携わっていると、自分よりもずっと偉大な何かに動かされていると実感することもある」
それは可南が、細見がコンサートマスターを務めるオーケストラの演奏を聴いた時に抱いた感覚に似ていた。大いなる存在。そして、自分はその一部であると。
「ねえ、可南さん。不思議だからって、『ない』わけじゃない。少なくとも可南さんの日常の中では、実際にそれが起こっているわけですから」
「病気かしら、幻聴かしらって、初めは悩みもしたんだけど、原因を考えても結局、わかりっこないし、だんだんとそれが当たり前になってきたんです」
「会話はいつでもできるんですか?」
「話しかけると、答えが返ってくることも、こないこともあります。あるいはふとしたときに、声が聞こえることがある。たとえばお風呂に入っているときや、眠る前とか、朝、目が覚めた瞬間も多いかな」
それからひとしきり、細見の問いは続いた。可南にとって、この秘密を誰かに話すのは初めてのことで、言葉にする中で考えがまとまり、自分自身がどう感じているのか、発見も多かった。これまでにも感じていたことだが、細見は聞き上手、いや卓越したインタビュアーなのだと確信した。
暮れなずんでいた空が急に暗さを増したので、可南は席を立って灯りをつけ、冷蔵庫から持って来たビールを細見のグラスに注いだ。細見は目だけで「ありがとう」と言って、ビールを喉に流し込み、ふーっと大きな息を吐いた。
「話はだいたいわかりました。いや、本当のことを言えば、全然わかりません」
そう言って、また破顔する。
「ただね、わかっていることが一つだけある。小腹が空いた、ということです。可南さんは?」
「お鮨を食べ終わった時は、もう夜はいらないって思ったのに、こうしてビールを飲んでいると、なんかつまみたいな、なんて、やっぱり食いしん坊なのね」
「そうこなくちゃ。じゃあ、料理研究家の大先生に出すにはこれしかない、という料理を作ります!」
細見はシャツの袖をまくりあげ、アイランドキッチンに立つ。可南は対面に立って、調理器具や調味料がどこに収納されているのかといった、細見の質問に的確に答えていく。
「よし、準備完了。まずはこの焼きそば麺を両面黄(リャンメンホァン)にします」
細見はテフロン加工のフライパンを使って、蒸し麺の両面をカリカリになるように胡麻油で揚げ焼きにしていく。
「普通はこれに餡をかけたり、あるいは中華スープを吸収させたりしますよね」
可南がうなずく。
「しかし、入れるのはこれ。酢醤油だけなんです。ここがこの料理『プレーン焼きそば』の最大のポイントです」
細見は菜箸をマイクのように持っておどけた。
「いいですか、先生。もっと美味しくできるアイデアがひらめいても、じっと我慢です。ほら、海綿状になった麺が酢醤油を吸って、クニュクニュになりました。なんと、これで出来あがりです」
皿に麺を盛ると、細見はそこに大量の鰹節と青ネギを掛けた。
「ねえ、このまま立って食べませんか」
細見の提案に、可南は満面の笑顔でうなずいた。
「これは……なんなの? スナックみたいな感覚で、いくらでも食べられちゃいそう。そして、ビールに合う!」
「そうでしょう? 腹を空かせた酒飲みには、これが一番なんです。あ、酒飲みなんて失礼だったかな」
可南は麺を頬張りながら首を横にふる。二人前の麺はあっという間に皿から消え去った。
シンクで皿洗いをして、まくった袖を元に戻した細見は、「じゃあ、これで」と言って、玄関に向かった。
「可南さんからご自宅に招かれたとき、期待がなかったと言えば嘘になります。でも、今日はこれで我慢します」
差し出された右手を、可南は静かに握った。細見はその手を軽く引き寄せ、可南の背中に左手を回して優しく抱いた。可南の息が止まる。瞳を閉じる。
ほんの一瞬の永遠の後、細見は深く一礼して、振り返らずに部屋を出て行った。