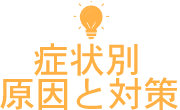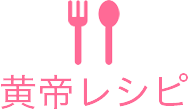それを聴く前と後とでは、自分という存在の全てが、すっかり入れ替わってしまうような演奏。可南にとってその日の九州交響楽団の公演は、まさにそんな体験だった。
ドヴォルザークの『新世界より』は、何度も耳にしてきたし、新婚旅行でヨーロッパを旅した時、ベルリン交響楽団の演奏で聴いたこともあった。しかし、今日のそれは可南にとって、これまで親しんできたものとは全く違うものだった。
オーケストラの演奏がことさら良かったのかもしれない。可南自身のこれまでの経験の重なりがクラシック音楽とようやく響き合うようになったからかもしれない。ヴァイオリンを奏でる細見嗣春の凛々しさに圧倒されたのかもしれない。
おそらく実際は、そうした様々な要素が、またとないタイミングとバランスで融合して生まれた感動なのだろう。可南は自分が大いなる存在と深い部分で繋がっていること、いや、その一部であることを実感し、心が震え、涙があふれるのを止めることができなかった。
細見に言われた通り、コンサートホールの楽屋に向かう。すれ違う人たちはおそらく誰もが関係者で、入場の時に「バックステージパス」を渡されていたものの、部外者である自分だけが浮いている気がして、可南は気後れしていた。
楽屋の入り口の前に立っていた女性に細見を訪ねてきた旨を伝えると、「お待ちください」と細くドアを開けて中に入っていった。細見が出てくるまでには三分とかからなかったはずだが、可南にはそれがひどく長く感じられた。
「ああ、可南先生!」
燕尾服の上着を脱ぎ、蝶ネクタイを外した細見は、顔の汗をタオルでぬぐっていた。身体中から熱を放射しているようで、可南は返事をすることも忘れて見とれてしまった。
「あ、ごめんなさい。可南先生なんて、馴れ馴れしすぎたかな。ほら、大将がそう呼んでいたから……」
「いえ、いいんです。『先生』が余計なくらい」
細見の視線が力強すぎて、可南は思わず下を向いて目を逸らす。
「可南先生、今日はありがとうございました」
「こちらこそ。あの、月並みな言い方で恥ずかしいけど、本当に感動しました。私、本当に……」
「よければ、指揮者とみんなを紹介しましょうか」
「とんでもない。私、ここに立っているだけで緊張しちゃって」
「可南先生、この後は?」
「この後? とくには……」
細見は人懐っこい笑顔で右手の人差し指を立てて、くるりと背を向けると楽屋の中に戻った。入り口の女性と目が合い、可南は困ったような微笑みをつくる。
慌ただしく出てきた細見は可南に小さな紙片を渡した。
「この店で待っててもらえませんか。片付けが終わったら追いかけます。そうだな、三十分くらい。先に適当に飲んでてください。それじゃあ」
「あ、あの……」
問い返そうとする可南を無視して、細見は楽屋の中に戻ってしまった。
店は福岡の中心部にあるコンサートホールからタクシーで二十分ほどの距離にある居酒屋だ。居酒屋と言いながらも、食材はとびきり高級である。だから支払いは料亭並みで、しかも決して良い立地とは言えないのに、連日満員のいわゆる予約の取れない店なのだ。遅い時間とは言え、席が取れたのは奇跡と言っていいだろう。
いや、もしかしたら、細見はこの展開を想定して、前から予約を入れていたのかもしれない。可南はタクシーの中でそう考えて、「どれだけ自信過剰な女なんだろう」と自嘲した。
店に着き、細見の名前を告げると、四人席の個室に案内された。メニューを眺める。多様な前菜から、肉、魚、揚げ物、焼き物、煮物、蒸し物、中には「山芋のお好み焼き」や「カマバター」といった庶民的な料理もあって、思わずくすりと笑ってしまう。
可南は自分なりに注文の流れをつくってみる。そして迷う。たとえば魚は「のどくろ」にするか、「きんき」にするか。それを塩焼きにしてもらうか、煮付けを選ぶのか。肉はロースにするか、ヒレにするか。黒豚という選択もある……。
「とても決められないわ」
思わず声にして呟いた。「この調子なら、いくらでも待つことができるな」と思いながらグラスのビールを飲み干した時、「可南さん、お待たせしました」と細見が個室の小さな扉を開けて入ってきた。白いVネックのTシャツに、かすかにインディゴの色味が残ったデニム姿の細見は、ステージ上の彼とは別人で、可南はその爽やかな佇まいに魅了されている自分を否定できなかった。