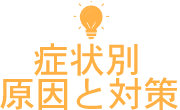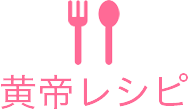「池之内可南(いけのうちかな)先生ですよね。いつもテレビで拝見しています。ぼく、先生のファンなんです」
突然の〝告白〟に可南は珍しく動揺したが、それを隠せるくらいには経験を積んでもいた。小さく微笑んで、落ち着いた低い声で返す。
「ありがとうございます。でも、ファンなんて言ってもらえる歳じゃないわ」
可南は今年の四月で六十四歳になった。男はどう見ても、十歳は歳下だ。ジャケットの上からでもわかる引き締まった体。張りのある黒髪に、白髪は見当たらない。まなじりのしわがなければ、四十代前半と言っても通用するだろう。
「いや、お世辞じゃなくて先生は我々世代の憧れですよ。そしてね、ぼく、先生を尊敬しているんです。先生はいつも定番の料理を紹介されるでしょ。その中にね、いつもどこかに一つだけ、嘘が入っているんです。嘘というか、料理の常識をちょっとだけ外れているというか。そこがなんとも言えない魅力なんです」
誰にも語ったことはないが、それは可南が料理研究家としての自分にいつも課していることだった。そもそも可南が週二回出演している、ローカル局制作のニュースワイドショーの料理コーナーは、この年代の男性が観るような時間には放映されていない。いったい誰なのだ。
状況を読んだのだろう、シャコにハケでツメを塗っていた大将が顔を上げた。
「可南先生、あれ、初めてだったかな。こちら九州交響楽団のコンサートマスターで、細見嗣春(ほそみつぐはる)さん」
思わず「へえ」とうなずいた可南に、細見は相好を崩して、「ああ、失礼しました。名乗ってもいなかった」と心地よく響く声で言った。
「お一人だったら、ご一緒してもいいですか」
「あら、お隣の方は?」
「ここで居合わせたんです」
「誰にでも、声をおかけになるのね」
「いや、そんなことはない。天に誓って言います。ぼくはそんな男じゃない。ねえ、大将?」
細見を見てニヤリと笑った大将は、何も言わずに捌いているアジに視線を落とす。
「もう、大将。人が悪い」
細見の少し甘えたような声に、可南はくすりと笑ってしまった。
「失礼ついでにお尋ねしますが、先生、そして大将、なんで夏の鮨が一番なんですか。二人だけで納得しちゃって、理由を話してくれないから」
「私たちの会話を聞いていらっしゃったんですね、背中で」
細見ははっと口を開いた後、片目をしかめて、バツの悪そうな顔をした。可南はその表情を、「子どもみたいでかわいい」と思った。今は東京で暮らしているひとり息子がまだ幼かった頃、嘘を見抜かれるとこんな顔をしたな、と思い出して、自然と顔がほころぶ。
「冗談ですよ。そうね、なぜ私が夏のお鮨が好きなのかと言うと……」
好物である貝類が総じてよくなること、コチやイサキ、カワハギといった白身魚の旬であること、唐津の雲丹、とくに黒雲丹のコクは日本一だと思っていること、最近はマイワシの旬が夏になっていることなど、細見の巧みな質問に乗って、可南は次々と理由を挙げた。こんなに夢中になって話したのは、どれくらいぶりだろう。
「好きなものを切ってもらうと、にぎりはそんなに食べられなくて。でも、旬の穴子は絶対にいただきたい。最後はヒモキュウで締めるの。他の季節じゃこうはいかないから」
「なるほど、得心がいきました」
「いえ、単に私の好みというだけです。一般論としては通用しないと思うわ」
「でも、先生の講義のおかげで、すでにしてぼくは夏の鮨の信者になりました」
細見がまっすぐに見つめるので、可南はそれが冗談なのかどうか判断がつかなかった。
そのあとは、可南の注文を「大将、ぼくも」と、細見が追随する形で食事が進んだ。
「先生、久しぶりに楽しい食事でした。いや、これまでの人生で最高の食事だったかもしれない。お礼に次のコンサート、招待しますので、ぜひいらしてください。いただいた名刺の、メールアドレスにメッセージを送りますね」
細見の誘いに、にこやかに礼を告げて、可南は店を後にした。タクシーに乗り込み、自宅のある通りの名を運転手に告げて、そっと瞳を閉じると、すぐに声が聞こえた。
〈恋をしたんだね〉
〈まさか、おかしなこと言わないで〉
〈非難しているわけじゃないんだ〉
〈ねえ、冗談で言ってるのよね〉
〈……〉
〈さっき私が話しかけた時、無視したでしょ。そして今も。ねえ?〉
その夜、可南が何度問いかけても、答えが返ってくることはなかった。