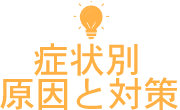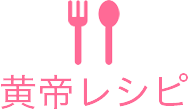可南は細見嗣春(ほそみ・つぐはる)と焼肉店にいた。いや、焼肉といっても、白木のカウンター席はまるで一流の鮨屋のようだ。引き算の内装の中で、正面に飾られた李朝の虎の民画が目を引く。カウンターの中の店主は白衣をまとい、厳しい目で肉を切り分けている。
「もはや、焼肉の概念を超えているよね」
細見はそう独り言のように言って、笑った。気まずい別れからの一週間、連絡を取らなかった二人だったが、可南が「会いたい」とメッセージを送ると、細見がこの店をセッティングした。暗い雰囲気になってもおかしくないのに、いきなり笑顔で緊張を解いてくれる細見を、可南は頼もしいなと思う。どこまでも優しくて、包容力のある人なんだ、九歳も年下なのに。
「実際、もはや焼肉とは呼べないと思う。だって、ここの主人はさ……」
細見は可南の耳元に口を寄せて、「いわゆる変態でね」と続けた。耳に細見の体温を感じて、可南は背中に甘い震えを覚えた。
「全国の畜産農家を回って、これぞと思ったら、何がなんでも相手を口説いて仕入れる。とくに赤身は抜群で、ぼくはこの店が日本一だと考えている。絶対に可南さんを連れてきたいと思っていたから、あのままにならなくてよかった」
沈黙。胸が詰まる。そこに三種類の赤身が載った白い長皿が供された。
「左から、山口県の高森牛のイチボ、熊本県のあか毛和牛のカイノミ、同じくシャトーブリアン。細見さんには焼き方のアドバイスはいらないね」
厳格な医者のようにも見える白衣をまとった主人は、そう言って、少しだけ口角を上げる。
「ぼくはなんと言っても、ゴールドトングですからね」
細見は自慢げに頷く。
「可南さん、このカウンター席は一見客お断り。さらに通い詰めて、免許皆伝となったら、この金色のトングの使用が認められるんだ」
なるほど、可南の前のトングは銀色である。
「だから、今日はすべてぼくが焼きます。料理研究家に対して、緊張するけど」
「そんな。うん、うれしい。お願いします」
カウンターに設置されたロースターで、細見はそれぞれの焼き加減を慎重に確認しながら、厳選された赤身を焼き上げていく。
同じ赤身と言っても部位が違うと、こうも味が違うのか。可南にとって、それは新鮮な驚きだった。共通するのはどれも味が深く、少しの嫌味もなく、噛み締めるほどに旨味が口の中に蓄積していく点だ。
「ぼくが肉を焼くのに忙しすぎて遠慮するかもだけど、耳は可南さんにちゃんと向いてるから、なんでも話してください」
可南は細見が選んでくれたカリフォルニアのピノ・ノワールを一口飲んで、呼吸を落ち着けた。
「四日前かな、主人と対話したんです。彼、もっと大きな魂のグループに帰ることになったって。だから、もう私とはこれまでのように話せないと」
「続けて」
「それで、私も、そして細見さんも、そのグループに属しているんだ、と。だから祝福するって」
「わかる気がする」
そう呟いた細見は肉から片時も目を離さない。トモサンカクやランプを堪能し、ミノを焼き終えると、肉はタレ味に変わる。高知県のあか毛和牛のバラ肉の薄切りを、細見はさっと炙るように焼き、器用にくるくると巻いて可南の皿の上に置いてくれた。
「演奏をしていると、自分が消えていくような感覚になることがある。これは意識してそうなるんじゃなくて、たとえば眠りに落ちるみたいに、向こうからやってくる感じ。ああ、ぼくはぼくじゃなかったんだ。こんなに崇高な存在だったんだ、と思う。とてつもない安心感と歓喜。もちろん、演奏が終わると、この体の自分に戻ってくる」
細見は真剣に話しながらも、次々と肉を焼いていく。新鮮なホルモンも絶品だ。
「だからね、ぼくらは誰もが、それは死者も含めて、大いなるひとつなんだと思うんだ。ただ、分離していると錯覚しているだけ。そして、その錯覚こそが、この地球に生きているってことなんじゃないかと。可南さん、ぼくたちは生きている。生きている間は、ぼくはぼくだし、可南さんは可南さんだ。分離しているから、愛し合うこともできる」
可南は黙って頷きながら、細見の話を聞いた。誰もそう思わないだろうが、それが細見の必死のプロポーズであることが可南にはわかった。
すっきりと澄み切った和だしにたゆたう冷麺を食べ終えた時、可南は「ああ、もうだめ。さすがに何も入らない」とつぶやいた。
「美味しいものを食べたときの、その表情。それこそが可南さんだ。じゃあ、いこう」
いつの間に会計を終わらせていたのか。細見は急ぐように可南の手を引いて店の外に出る。
「今日はぼくの部屋に来てほしい」
秋の風が吹いた。可南は答える代わりに、繋いだ手に力を入れて、細見の肩にそっと頭を預けた。