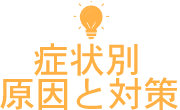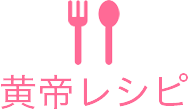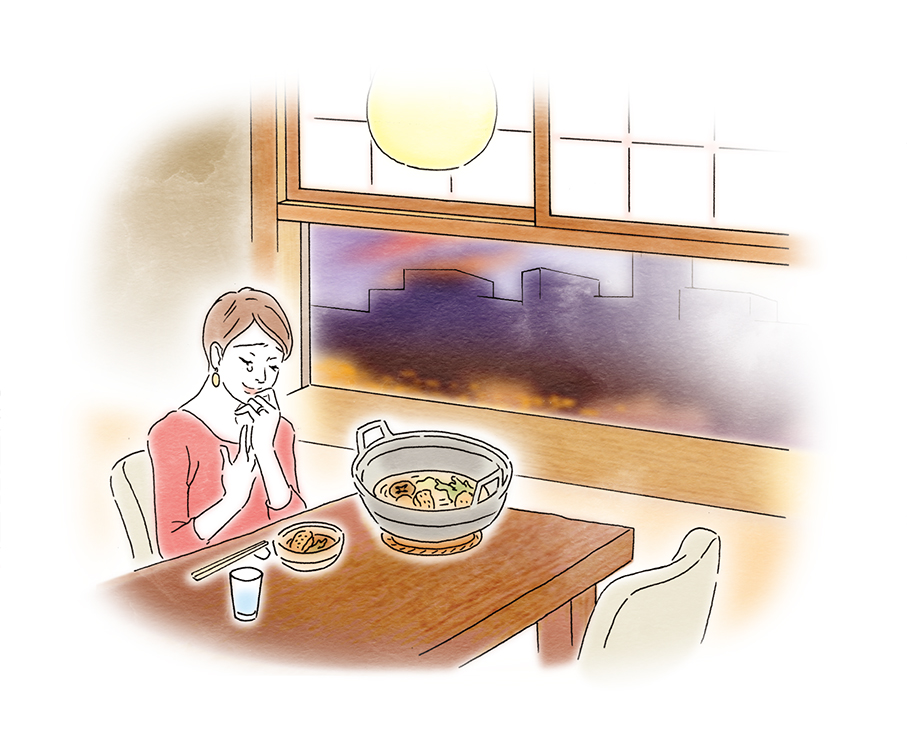
連絡がなくなって三日が経つ。
互いに仕事があるから、SNSでの断続的なやりとりではあったが、細見はこれまで可南に短いメッセージを日に数回は送ってくれていた。とくに食事の画像を送り合うのは、可南にとってのささやかな、しかし大切な楽しみとなっていた。
それが途絶えることが、こんなに悲しいなんて。細見と出会う以前は当たり前だった日常が、どこまでも空疎で味気なく感じられる。
食欲もない。乙女の恋煩いじゃあるまいし、と思いはするが、今日だってふと気づくと、何も食べないまま午後2時になっていた。思わずため息が出る。
「お素麺でも茹でますかね」
そう言って、キッチンへ向かう可南の脳裏に久しぶりに声が響いた。
〈だめだよ、ちゃんと食べないと。おいしいものへの貪欲さが、すなわち君なんだから〉
正(ただし)らしい言い回しだ。可南は「確かに」と声に出して小さく笑う。
〈今夜はさ、久しぶりに水炊きを食べに行こう。まあ、俺は口がないから食べられないけどね〉
「口がないのに、なぜ話せるの?」
軽口に付き合ってみる。
〈なんというか、これは形而上的な口なんだよ。つまりその意味では好物の水炊きを君と一緒に、形而上的に食べられるとも言えるね。ほら、いつもの個室を予約して〉
正の行きつけだった店に電話をかける。個室は2名からだが、女将は「可南先生だから特別に」と言ってくれた。
創業百年を超える老舗の店構えはさすがに風格があり、案内された部屋の窓からは夕陽にきらめく那珂川が見える。ほっと息をついたところに、女将が入ってくる。
「なんだか、向かいに正さんがいらっしゃらないのが不思議。もう何年になるかしら」
「ちょうど二年です」
「ああ、早いものね……なんて、私が感傷的になってどうするのって話よね」
二人はくすくすと笑った。可南にとっては三日ぶりのことだった。
正はコースではなく、いきなり水炊きから始めるのを好んだ。まずは創業から継ぎ足され続けているスープが供される。鶏ガラを十時間以上炊き込んだ白濁スープに、鶏のぶつ切りを柔らかく炊いた透明なスープを合わせて仕上げる。濃厚だがキレがよく、鶏スープ独特の香りが、あさつきのそれと見事に調和する。
〈いやあ、たまんないね。このかぐわしさ〉
正にそう言われて、可南は一気に空腹を感じた。熱い汁を一口。喉から胃に落ちて、さらに全身に広がるのを感じる。滋味とはこのことだ、と可南は思う。
〈そうそう、その笑顔こそ君だ。さあ、食べて、食べて〉
生後三カ月以内の、その日の朝に捌いた雄鶏だけを使うという鶏の身はやわらかく、箸を入れるだけでほろほろと骨から離れる。角のないポン酢醤油に軽くつけて、じっくりと炊き上げたからこその鶏の甘みをゆっくりと味わう。
〈可南、俺、なんだか帰れそうな気がしている〉
〈帰る? この世に? 幽霊になって?〉
いやいや、と正は笑う。
〈うまく説明できないんだけど、個を超えた、もう少し大きなグループというか……〉
〈それは魂の……〉
〈そうだな。その表現が一番近いと思う〉
〈じゃあ、もうあなたとは、こんなふうに会話できないの?〉
〈たぶん、俺個人とは……ただ、その魂のグループとは交信できるはず。というのも、君もそのグループの一員だから〉
〈私も?〉
〈そう。もっと言えば、彼も同じグループだ〉
正の言っているのが、細見であることは間違いなかった。
〈だから何というか、気兼ねしないでほしいんだ。君たちがパートナーとなって成長してくれれば、それは俺にとっても成長なんだよ。そのことがわかって、君に対する執着も、嫉妬心も、驚くくらいに消えた。だから、帰れそうな気がするんだ。つまり、この2年間は、俺にとっても準備期間だったんだよ。もちろん、君にとっては新しい恋に向かっていくための〉
〈さびしくないの?〉
〈さびしくない、と言えば嘘になる。でも、俺は消えてなくなるわけじゃないし、君を見守り続けることはできる。それはそれで、悪くない。ねえ、箸が止まってるよ。そろそろ雑炊を注文したら?〉
可南は「こんな大切な話をしているのに」とおかしくなって笑った。笑いながら、涙が止まらなくなった。
〈雑炊はさ、スープを継ぎ足してもらって、サラサラとお茶漬けくらいの感じにするのが旨いんだ〉
正の声も笑っていた。そして、同時に泣いていることが、可南にははっきりとわかった。
〈あなたの好みは知ってる。ほんの少しだけポン酢醤油を入れるのよね〉
しかし答えは返ってこなかった。〈ねえ〉と何度も念じる。声にも出した。しかし、答えは――二度と、返ってこなかった。