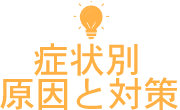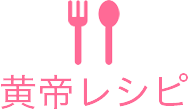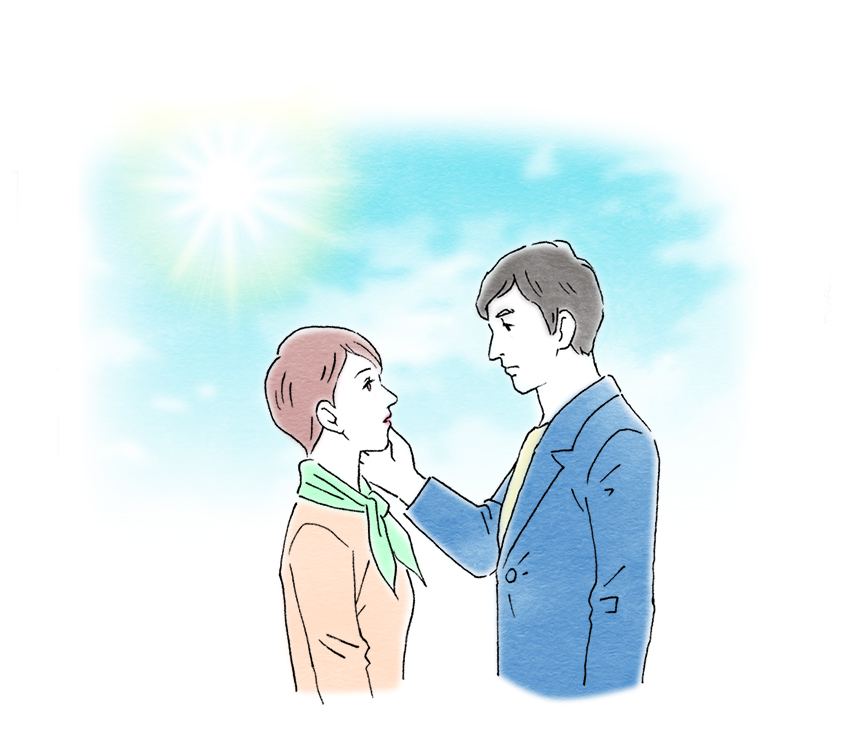
抜けるような日曜日の空を背に、赤い電車は西へとのどかに走る。
福岡市の都心部から佐賀県の唐津までは一時間半ほどの距離だが、こうして電車に揺られると、旅の気分は一気に高まる。揺れに合わせて自分の肩に細見嗣春の硬い腕が当たって、その部分だけが熱くなる感じを池之内可南はときめきながら楽しんでいた。
「ツウの可南さんをお鮨屋さんに誘うのは緊張するな」
「ツウだなんて。好きなだけだから」
「ねえ、唐津でお鮨を食べたことは?」
何年前だろう。一度だけ正から連れて行ってもらったことがあった。取引先の経営者夫婦と一緒で、だから接待という面が強かったのだが、そのことを細見に告げるかどうか可南は躊躇って、不自然な間が空いた。
「いえ、初めて」
ようやく口をついて出た言葉は、自分でも意外なものだった。
〈あれ、なんで嘘をつくの? たぶん、あの店だよ。彼、さっき「カウンター7席だけ」って言っていたし〉
「ちょっと、なに……」
思わず出た声に、細見が「どうしました?」と尋ねる。
「あ、ごめんなさい。ちょっと他のことを考えていて……」
ちょうど電車が唐津駅に着いたので、不自然な状況も、なんとかごまかせた。可南は心の中で「話しかけないで」と正に何度も語りかけたが、答えは返ってこなかった。
秋めいてきたとはいえ、駅から十分ほど歩くと軽く汗ばんだ。店の暖簾をくぐり、白木のカウンターに座った細見はビールの小瓶を注文して二つのグラスにぴったり注ぎ分けた。
「ほんとは最初から日本酒で行きたかったんですが、この陽気だから一杯だけ。ご主人、次は『北雪』をお願いします」
わかりましたと頷いた店主の柔和な瞳の奥には、しかし、厳しさ、繊細さ、一本気が読み取れる。
「ここはね、とにかく酒のあてが秀逸なんです。とくにぼくは塩辛なんだ。イカの塩辛はもちろんだけど、栄螺の塩辛、魚のはらわたは、もうなんでも塩辛にしちゃうし、それで言えば大将の鮎味噌は……ああ、ほら、想像するだけで酒が飲める」
可南は細見の話を楽しく聞きながら、しかし、正が話しかけてくるんじゃないかという想念に気を取られてしまう。
「地物の刺身もいいし、鯨もいいしね。握りまでたどり着く前に、どうしても酔ってしまって、大将から叱られるんです。昔はもっと怖かったから、『おい、ここは鮨屋だぞ。鮨を食わねえでどうする!』ってね」
細見は「自分の店」に連れてきた高揚感からか、いつになく饒舌だ。可南はふぐの薄造りにひらめのキモを巻いて口に運び、素材の味と切り方、酢と醤油、ネギの量といったすべてのバランスの妙に主人の腕の確かさを感じていた。一方で、今ひとつ味に集中できていない自分を認識してもいた。
「心ここにあらず」
「え?」
「今日の可南さん、目の前にいるのに、すごく遠い。そして、この店、初めてじゃないでしょう?」
細見は背中を向けて握りの用意をしている主人にはギリギリ聞こえないくらいの小さな声でそう言った。可南もやはり小声で「ごめんなさい」と返した。
「いや、謝らないで。でも、ここからは最高の鮨を楽しみましょう」
細見は可南を見つめて、きゅっと口角を上げた。アオリイカ、車海老、鯨の赤身漬け、しめ鯖、赤貝、ウニの細巻き……口の中に入れた途端に見事にほどけるかためのシャリ。砂糖を使わず、赤酢と塩だけで仕上げた酢飯を味わううちにネタと一体化していく過程は見事の一言。可南は絶品の穴子を目を閉じて、その味の隅々まで堪能しながら、体中に幸せが満ちるのをうっとりと感じた。そうだ、これを「円熟」というのだ。
「ああ、最高だった。細見さん、ありがとう。そしてごちそうさま」
店を出た可南は大きく深呼吸した後に、満足そうな顔でそう言った。昼下がりの、しかしまだ高い太陽が、可南のまつ毛を輝かせる。
「可南さんはきれいな人だ」
細見は愛おしそうな目で、しかし、哀しみをたたえた声で呟いた。可南は驚いた顔で、細見を見返す。
「外見ももちろんなんだけど、なんというか生き方がきれいな人なんだ。そして、そういう人は心が透けて見える」
「どういう意味?」
「可南さんは、ずっと何かを気にしている。ぼくと一緒にいることは、誰かにとって悲しいことなんですか。それとも可南さん自身が苦しいんですか」
「苦しいなんて、そんな……」
うつむく可南のあごをやさしく持ち上げて、細見は視線を合わせる。
「ぼくは可南さんが好きだ」
〈いよいよ、時が来たな〉
可南は細見の目を見ながら、正の声を聞いた。
「わかったわ。あなたがこれまで聞いたことの中でも、とりわけ奇妙な話になると思います。私の家に来てもらえますか」
細見は神妙な顔でうなずいた。