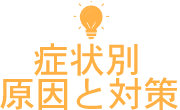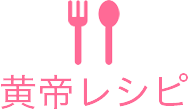〈そろそろ、お店に着くわ〉
〈そうだね。じゃあ、しばらく話しかけないようにするから〉
〈ありがとう〉
〈ゆっくり楽しんでおいで〉
まぐろ壁――官能の色。
十メートル近いカウンターは継ぎ目のない尾州檜で仕立てられた一枚板で、視線を上げると、雲をモチーフにした和の照明が朱色の壁をやわらかく照らしている。
「いらっしゃい」
板前たちの威勢の良い声が高い天井に反響する。
池之内可南(いけのうちかな)は福岡でも屈指の鮨屋と言われるこの店の壁を、ひそかに「まぐろ壁」と呼んでいる。トロを思わせる鮮やかな色を見るだけで、これから三時間ほどをかけて演じられる美食劇場の幕開けが予感され、胸がときめき、決まって口中に甘い唾液があふれるのだった。
十八時を過ぎたばかりだというのにカウンター席はすでに埋まっている。財界人が多い。隣に座る着物姿の女性たちは自然と背景の一部となる。政治家や芸能人も常連なのだが、彼らは人目につかない別の入り口から二階の隠し部屋に入れる仕組みである。
大将と目が合う。七十歳をとうに過ぎているはずだが、枯れたところなど微塵もなく、むしろ腕一本だけで生き抜いてきた男だけが持つ独特の色気を漂わせている。その眼光の鋭さを隠すように苦味を含んだ笑顔を可南に投げながら、顎の微妙な動きだけで自分の正面の席へ座るように促した。
「可南先生、お久しぶり」
「あら、ご挨拶だこと。先週もうかがったわ」
「この店は先生の〝お茶の間〟なんだから、毎日来てもらわないと」
「じゃあ、そうできるくらいのお値段にしてくださいな」
軽口を言い合って笑うのはいつもの約束事だ。
「何からいきましょう」
「そうね、その白身はコチ? ああ、美しいわね」
店主が決めた「おまかせ」のみ、という店が増える中で、まるで居酒屋のように、煮物、焼き物、蒸し物など、様々な魚料理を、お客の注文に応じて提供する福岡独自の鮨屋文化を、この店は貫いている。一人で訪うことが多い可南にとっては好都合だ。可南の好みやスタイル、胃袋の大きさまでを知り尽くしている大将は、だから刺身を一枚ずつ、つまみを少量で出してくれる。
鮨の時は清酒を飲むと可南は決めている。福岡の地酒で、吟醸ではなく純米酒という条件だけを伝えていて、あとは店に選んでもらう。
コチの歯応えのある身を奥歯で噛むと、淡白な味わいの中から、甘味と滋味が薄く、しかし確実に染み出してくる。そして、その微かな旨味を酒で増幅させるのだ。目を閉じた可南から恍惚の吐息が漏れる。
「コチ、よかったでしょ。ああ、そうだ。今日は可南先生の好物の天然ものが入ってますよ」
大将がうなぎの黄金色の腹を見せながら言う。
「ああ、いいわね。じゃあ、あとで白焼きにしていただくとして、次はしゃこと、それからあげまきを炙ってもらえるかしら。あと、煮鮑も。できれば端っこがいいわ」
言わずともわかっているとでもいうように、大将はゆっくりとうなずいた。
「はい、じゃあ、先に煮鮑。今日のはね、マダカ鮑」
「マダカ鮑……」
この年になっても、そして、こんな仕事をしていても、意外と知らないことは多いのだ、と可南は自省する。
「そう、幻の鮑。珍しく手に入ったんです。理想的な大きさだね。これは旨いよ」
「お値段を聞くのが怖い」
「確かに。聞かないほうがいいかも、ですね」
最高級の鮑の、海の美しいところだけを凝縮した香りが鼻腔を抜ける。添えられた肝がまた絶品だ。ねっとりと舌にまとわりついた濃い旨味は、しかし意外とあっさりと引き下がり、酒とともに爽やかに流れていく。
「ああ、はあ……幸せ」
可南は小さく唸るように、そう呟いた。
「好きなものを食べる時の可南先生は本当にきれいだね」
「やめてよ。何も出ませんよ。ねえ、大将、私ね、初めて言うけど、実は『夏のお鮨が一番』っていうのが持論なの」
「へえ、それは変わってますね。でもね、実は私もそう思っています」
「あら、私たち意外と気が合うのね」
「だめですよ、美しき未亡人さま。私は妻子のある身ですから」
一瞬、大将と二人で暮らす自分をイメージした可南が声を出して笑った瞬間、隣の席で背中を向けていた男が急に振り向いた。
「池之内可南先生ですよね」
突然のことに、可南は男の端正な顔立ちを小さな驚きとともに見つめた。
可南は自分の鼓動を意識した。
〈なんなの、これ?〉
可南は心の中でそう問いかけたが、答えが返ってくることはなかった。