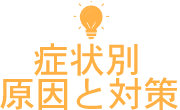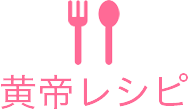「ああ、ここが可南さんの仕事場なんですね」
細見嗣春は目を見開いて、二十畳はあろうかというダイニングキッチンを見回した。
「すごい。こんなに広くて長いアイランドキッチンは初めて見ます。感動だな。ここであの料理の数々が生み出されるんですね」
うれしそうに話す細見は、興奮しているのか、いつもより早口だ。
「まあ、でも私はここに一人で暮らしているから、台所でもあるわけで……」
池之内可南ははしゃぐ細見を愛おしく感じながら、照れもあってそう言った。
「いやいや、だって可南さん、この設計はすごい。ものすごく考えられている。可南さんの美意識が生み出した、ちょっとした芸術作品ですよ」
「そんな大げさよ」
「いや、待って」
急に真剣な顔をした細見からまっすぐに見つめられると、可南は思わず緊張してしまう。
「ぼくが芸術だって言うときは真剣です。ぼく、これでも芸術に生きてるんですよ、可南さん」
「ごめんなさい」
「怒ってるわけじゃないんだ。このキッチンのことを、本当に素晴らしいと思っていることを、可南さんにわかってほしいだけで……」
「ありがとう」
確かに可南は、キッチンの設計にとことんまでこだわった。調理スペースはもちろんだが、最大のポイントは背面にある大型の収納スペースだ。
ここに器や調理器具が格納されているのだが、天井から床までの巨大な木製の引き戸は、無垢材に柿渋を塗り重ねた和にも洋にも感じられるもので、一見すると壁のようでありながら、しかし、その重たい塊は、女の力ですっとしなやかに動くのであった。細見はその軽さを、何度も自分で確かめていた。
「キッチンでどんな調理をしていても、振り向くだけで、欲しいものの全てが手に取れる。でも、収納が現れるのは一瞬のことで、閉まればまた、この美しく機能的なキッチンだけが空間から浮かび上がる。可南さん、これはすごい。本当にすごいよ」
「そんなことに気づいてもらったのは初めて。主人だって……」
その瞬間、唐津の鮨屋を出た時の気まずさが一気に蘇った。この部屋で話すと決めてから、電車の中でも、タクシーの中でも、自然といつものような会話が弾んだ。料理のこと、音楽のこと、文学のこと、映画のこと……それは可南にとって、知的好奇心が満たされる幸せな時間だった。
秘密を明かすと決めたことを忘れたわけではなかった。それでも、細見のジョークに笑って、彼の匂いを感じているときは、そんな時間が永遠に続くようにも思えたのだ。
〈さあ、いよいよだね〉
〈あなたは黙ってて〉
〈黙ってなんかいられないよ。だって、自分の話なんだからね〉
〈あなたには関係ない〉
〈関係ないってのは言い過ぎだろう〉
〈だって、この世にいないんだから〉
〈でも、こうして話している。今、俺たちが会話しているのは、現実じゃないか〉
「可南さん?」
細見が軽く眉をしかめた。
「ごめんなさい、私……のどがかわいちゃった。ビールでも飲みませんか。ねえ、そこに座って」
細見は黙って、十人くらいならば楽にもてなせる木製のテーブルと同じ素材で作られた椅子のうちで、キッチンに一番近い場所を選んで座った。家具のデザインを見ながら、触れながら、撫でてアールを確かめながら、それらは彫刻家によって製作された一点ものであることを確信した。
細見の背面はベランダに続く南向きの大きな窓で、それも天井から床まで、大胆に大きく取られていた。いまだ弱まりを見せない初秋の夕方の太陽光線が、照明をつけていない部屋の中を互いの表情がはっきりと読み取れるくらいには明るく照らしていた。
可南は一瞬迷って、細見の対面に腰掛けた。薄張りのグラスをコースターの上に置いて、チェコのピルスナービールを注いだ。
「これ、際限なく飲めるんだよなあ。あと、可南さん、ぼくあとで『焼きそば』を作っていいですか。もうね、これ以上ないって自慢のレシピがあるんです。さっき冷蔵庫を見たら、麺があったから」
細見が緊張をほぐそうとしてくれていることがわかって、可南は頷きながら、そのやさしさに胸が熱くなった。
「細見さん、私が狂ってるって思うなら、そう言ってもらっていいし、気持ち悪いと思ったら、すぐに部屋を出て行ってもらってもかまわない。その覚悟はあのコンサートの夜からしているから、私はきっと傷つきはするけど、でも、そんな自分を自分で守ることくらいはできるから」
「まだ、出会ってそんなに時間は経っていないけど、ぼくは可南さんのことをちゃんと見てるつもりでいる。だから……うまく言えないけど、安心して話してほしい」
「ありがとう」
可南の瞳から涙が一筋、銀色の糸となって頬をつたった。
「私、亡くなった夫の声が聞こえるの」